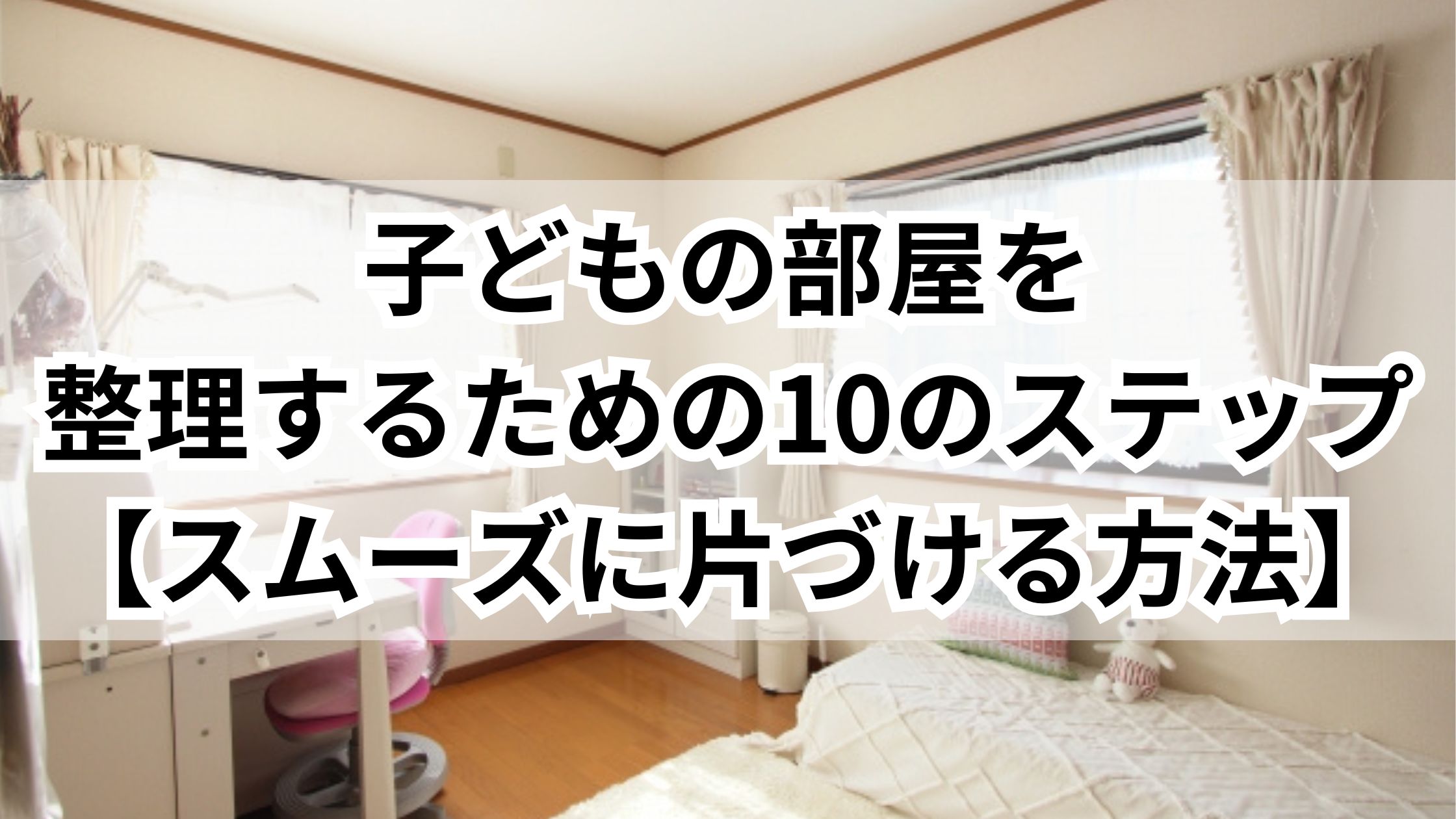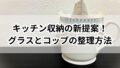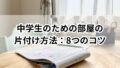子どもの部屋を整理整頓できるようになるためには、親が適切にサポートすることが重要です。
本記事では「子どもの部屋整理のための10のステップ」を具体的にご紹介しますが、最大のポイントは「子どもが主体的に整理できる環境を作ること」です。
親が勝手に片付けたり、高い目標を押し付けたりするのではなく、子どもの目線に立った収納方法を考え、体験を褒めることで、自発的な行動を促すことが鍵となります。
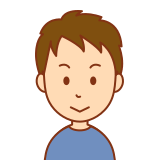
この記事を読めば、片付けが親子でできるアプローチが見つかるはずです。忙しい日々の中でも実践できる工夫を知り、子どもに整理整頓の習慣を無理なく身につけさせましょう!
この記事を読むメリット:
- 子どもが自分で片づけられるようになる:子どもが自分で片付けを行うことで、自分の持ち物や空間に責任を持つ習慣が身につきます。
- 親子のコミュニケーションが深まる:親子で一緒に片付けに取り組む時間を持つことで、自然と会話が増え、関係がよくなります。
子どもの部屋整理のための10のステップ

部屋の片付けを子どもに教える10のステップは以下の通りです。
- 部屋が片付いていないことをただ単に指摘しない
- 親が収納場所と収納アイテムを準備する
- 子どもの視点で適切な収納場所を設定する
- 親子で一緒に片付けを行い、繰り返し教える
- 物の量を親が適切に管理する
- 子ども専用の収納場所を決める
- 子どものスペースは勝手に整理しない
- 物を勝手に捨てない
- 完璧な整理整頓を子どもに求めない
- 上手に整理できたら、その時を褒める
それぞれのステップについて詳しく説明します。
部屋が片付いていないことをただ単に指摘しない
親が収納場所と収納アイテムを準備する
子どもの部屋を整理する上で、収納場所と収納アイテムの準備は親が行うことが望ましいです。
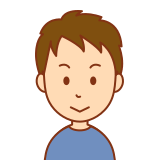
子ども自身がまだ整理整頓の技術や管理能力を完全に身につけていない場合、適切な収納場所の設定と、使いやすい収納アイテムの提供は、彼らが自分の持ち物を整理する大きな助けとなります。
- まず、部屋を見渡して、どのようなアイテムが必要かを考え、それに合った収納スペースを確保しましょう。
- 例えば、本や教材は読みやすい場所に、おもちゃは子どもが自由に取り出せる低い棚に配置するといった具体的な計画を立てます。
- また、小さな箱やバスケットを用意して、小物や工作の材料を分類しやすくするのも良い方法です。
このようにして、親が示した収納の模範を通じて、子どもは整理整頓の基本を理解し、次第に自分で部屋を整頓された状態に保つスキルを発展させることができます。
子どもの視点で適切な収納場所を設定する
子どもの部屋を整理する際には、大人の視点ではなく、子どもの目線に立って収納場所を設定することが重要です。
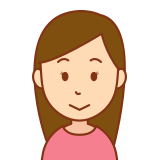
子どもの身長や力を考慮しない収納では、片付けの手間が増え、結果的に散らかったままの状態が続いてしまうこともあります。
- 例えば、高い棚や背の届かない場所に収納するのは避けましょう。特に重い本やおもちゃを持ち上げることが難しい小学校低学年の子どもには、重い物を低い位置に配置することで使いやすさを確保できます。
- また、収納スペースに手が届く範囲を考慮し、自分で出し入れがしやすい環境を整えることが大切です。
さらに、子どもが物の定位置を簡単に覚えられるように、収納ボックスや棚には分かりやすいラベルを付けましょう。イラストや色分けなどを活用することで、小さな子どもでも直感的に理解しやすくなります。ファイルホルダーや仕切りも、種類別に整理する際に役立ちます。
このように、子どもの視点を意識した収納の工夫をすることで、自分で片付けを行う習慣が自然と身につき、親子双方にとってスムーズな整理整頓が実現します。
親子で一緒に片付けを行い、繰り返し教える
子どもに片付けを教える際は、親子で一緒に取り組む時間を作ることが最もよいです。
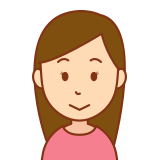
子どもは、親の行動を観察し、その手順や方法を学び取る傾向があります。実際に片付けをする場面を共有することで、子どもは自然と整理整頓の習慣を身につけることができます。
- このプロセスでは、まず親が率先して模範を示すことが重要です。
- ただ指示を出すだけではなく、一緒に物を分類したり、収納場所を決めたりする過程を共有することで、子どもは片付けの流れを理解しやすくなります。
- また、片付けの中で「なぜこれをここに置くのか」「どのようにすれば取り出しやすいか」といった会話を交えることで、整理の方法を深く学ぶことができます。
忙しい日々の中で片付けの時間を確保するのは難しいかもしれませんが、短時間でも良いので定期的に行うことが大切です。例えば、週末の朝や夕方に「一緒に片付けタイム」を設けるのもおすすめです。繰り返し行うことで子どもは徐々に自分で片付けるスキルを身につけ、習慣化していきます。
このように親子で片付けに取り組む時間を共有することで、片付けが日常の一部となるでしょう。
物の量を親が適切に管理する
子どもの部屋を整った状態に保つためには、物の量を親が適切に管理することが大切です。
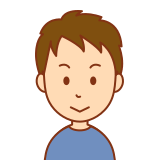
特に、子どもは「これが必要かどうか」という判断が難しい場合が多く、結果として物が増えすぎ、収納スペースをせまくしてしまうことがあります。
まず、親が定期的に子どもの持ち物を見直す機会を設けるのがよいです。その際、「今使うもの」「時々使うもの」「もう使わないもの」のようにカテゴリー分けをしながら整理を進めます。
例えば、季節外れの服や一時的に使用しないおもちゃは、別の収納スペースに移動させることで、日常的なスペースを確保できます。
さらに、物が増加しないために、新しい物を手に入れる際には収納スペースや必要性を一緒に確認する習慣をつけると良いでしょう。
子ども専用の収納場所を決める
子どもの部屋を整理する際には、子ども専用の収納場所をしっかりと決めることが重要です。
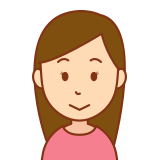
収納場所が明確に定まっていないと、子どもはどこに何を片付ければよいのか分からず、結果的に散らかりやすくなります。
- まず、子どもの持ち物を種類ごとに分類し、それぞれに合った収納スペースを設定しましょう。
- 例えば、「絵本はこの棚の一番下」「おもちゃはこの箱」「学校の道具はデスクの引き出し」といったように、具体的な場所を親が決めてあげると良いです。収納スペースは子どもが簡単に使える高さや配置にすることがポイントです。
さらに、収納場所にラベルを貼るのもおすすめです。特に、小さな子どもの場合、イラストや写真付きのラベルを使うことで直感的に覚えやすくなります。また、子どもと一緒にラベルを作ることで、収納への関心を持たせるきっかけにもなります。
親が一度収納場所を設定した後も、子どもと話し合いながら必要に応じて変更することも忘れないようにしましょう。
整理整頓の手本を親が示す
子どもに整理整頓を教えるためには、親自身が模範となることが重要です。
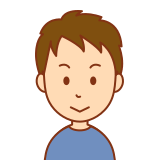
親の部屋が散らかっている場合、「片付けなさい」と言葉で伝えても、説得力を持たせることは難しいでしょう。子どもは、親の行動を細かく観察し、その行動から学ぶことが多いのです。
まず、親自身が整理整頓を心がけ、普段から整った環境を保つことを意識しましょう。
たとえば、自分の作業デスクやリビングの収納スペースなど、子どもが目にする場所を整えることから始めてください。「使ったものは元の場所に戻す」「必要なものだけを置く」といった習慣を見せることが、子どもへの自然な教えになります。
また、片付けをする際には子どもにそのプロセスを見せるだけでなく、時には一緒に作業する時間を設けるのもおすすめです。たとえば、「この本はよく読むからここに置いておくね」「これは使わないからしまおう」と声に出して行動することで、片付けの考え方や方法を具体的に伝えることができます。
親が整理整頓の手本を示すことで、子どもは片付けが「やらされること」ではなく、自然と身につけるべき習慣であると理解します。
子どものスペースは勝手に整理しない・物を勝手に捨てない
子どもの部屋が散らかっているからといって、親が勝手に整理したり、物を捨てたりするのは避けるべきです。
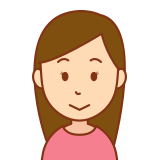
まず、親が代わりに片付けてしまうと、子どもは自分で整理整頓をする必要性を感じなくなります。「どうせ親が片付けてくれる」と思うようになると、自発的な片付けの習慣を身につける機会を失ってしまいます。
子どもの物を整理する際には、必ず子どもを巻き込みましょう。片付けの手順を一緒に考え、「このおもちゃはまだ使う?」「これは別の子に譲るのはどう?」など、質問を通じて整理のプロセスに参加させることが大切です。
このようなやりとりを通じて、子どもは物の管理方法を学び、自分の意思で整理整頓ができるようになります。
完璧な整理整頓を子どもに求めない
子どもの部屋を片付ける際、親が完璧な整理整頓を求めるのは避けたほうが良いでしょう。
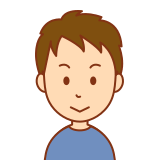
子どもにとって片付けは、学ぶべき新しいスキルの一つです。そのため、親の理想とする結果を最初から求めるのではなく、子どもが少しずつ学んでいく過程を大切にすることが重要です。
片付けを習慣づける初期段階では、親の期待の10〜20%が実行できれば十分です。
たとえば、おもちゃがすべて棚に戻されなくても、一部だけでも所定の場所に収まったのであれば、それを認めてあげましょう。子どもが「自分でもできる」という達成感を得られるよう、ポジティブなフィードバックを与えることが大切です。
また、完璧さを求めてしまうと、片付けが「面倒」「難しい」と感じさせることにもなりかねません。片付けのプロセス自体に前向きに取り組めるように、少しずつ達成可能な目標を設定し、できた部分に目を向けて褒めることを心がけましょう。
上手に整理できたら、その時を褒める
子どもが片付けや整理整頓を上手にできたときは、その努力をその場で褒めることが大切です。
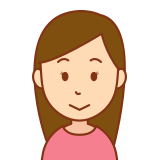
褒めるタイミングを逃さず、子どもが「自分でやり遂げた」と感じた瞬間に声をかけることで、できたことをしっかり印象づけることができます。
褒める際には、「すごいね、上手にできたね」「ここをこんな風に片付けたんだね」といった具体的な言葉を使うと、子どもは自分の行動をよりポジティブに認識できます。ただ「えらいね」と言うよりも、子どもの努力や工夫を具体的に評価する方がよいです。
まとめ

子どもの部屋を整理することは、ただ部屋を整えることだけでなく、子ども自身の整理する力を育む大切なプロセスです。本記事でご紹介した10のステップを実践すれば、親子で片付けに取り組めるだけでなく、子どもが自発的に整理整頓を行う力を身につけられるでしょう。
大切なのは、親が一方的に指示を出すのではなく、子どもが主体的に考え、行動できる環境を整えることです。小さな成功を一緒に喜びながら、片付けを共有してください。このプロセスを通じて、子どもは自分の空間を大切にする意識を育み、親子の関係もさらに深まるはずです。
ぜひ、このステップを取り入れ、家庭全体でよりよい部屋を作り上げてみてください。